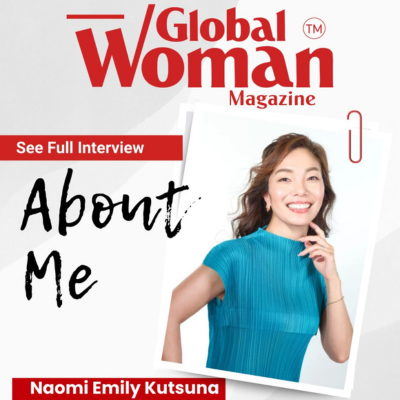Naomi Emily Kutsuna: 壁と屋根を越えた向こうに
Naomi Emily. Kutsuna は、コミュニティ(家)づくりの意味を再定義しています。日本人の起業家であり、妻であり、母であり、米国拠点の不動産開発会社の副社長でもある彼女は、鋭いビジネス戦略と「家族がただ暮らすだけでなく、本当に“居場所”だと感じられる空間をつくる」という真摯な使命を融合させています。大規模なライフスタイル・コミュニティからラグジュアリー住宅に至るまで、彼女 のプロジェクトはすべて意図をもって設計され、つながりや機会、そして“家”であるという感覚が、壁や屋根の枠を超えて豊かに育まれていく場所となっています。
Q: 投資を、単なる金銭的リターン以上の——誰かの人生への「贈り物」だと捉えていらっしゃいます。この哲学はどのように形づくられたのですか?
A: この哲学が形になり始めたのは、私が母になった時です。子どもを育てることは何にも代えがたい経験でしたが、同時に、社会に本当に意味のある影響を生み出す仕事を続けたい、と気づきました。
不動産開発を始めてから、私たちがつくっているのは単なる「家」ではなく、人々の毎日の暮らしの土台なのだと実感しました。あるご家族が「ここに引っ越してから、子どもが本当に楽しそうなんです」と話してくれたことがあります。その一言は、どんな財務報告よりも私の心を深く動かしました。
こうした瞬間が教えてくれたのは、数字だけが物語のすべてではないということ。大切なのは、人々がどう暮らし、どうつながり、コミュニティの中で支えられていると感じられるかです。だから私は、投資を単なる金銭的リターンではなく、誰かの未来への「贈り物」だと捉えています。私にとって、あらゆるプロジェクトは、物語が育ち、感謝が巡り、人生が花ひらく“家”をつくることなのです。
Q: 母親としての時間から不動産開発へと舵を切った原動力は何でしたか?その転機は、あなたの人生の方向性をどう変えましたか?
A: 私にとっての大きな転機は、母になったことでした。母になる経験は人生で最も変革的で、本当に大切なものが何かを見せてくれました。子どもと過ごす時間は何ものにも代えがたい一方で、家族の枠を超えて社会に貢献したいという強い想いも芽生えたのです。生きがいと使命感を感じられる仕事がしたい――そう思いました。
不動産開発に進んだのは、その想いがあったからです。私たちがつくるのは物件ではなく、家族が伸び伸びと暮らせる“環境”そのもの。そこで初めて、私生活と仕事の方向性が一本の線でつながった感覚がありました。
この転機は私の進路を根本から変えました。母としての自分と、コミュニティを育てる開発者としての自分が結びついたのです。今では、すべてのプロジェクトが「人が安心して帰れる場所、支え合える場所、インスピレーションを得られる場所をつくる」という、職業的挑戦であり個人的使命でもあります。
Q: 米国で日本人女性としてプロジェクトを率いるにあたり、ビジネスやコミュニティづくりで文化の違いをどう乗り越えてきましたか?
A: 文化の違いは、挑戦であると同時に大きな贈り物でもあります。日本で培った「敬意」「辛抱強さ」「細部への配慮」といった価値観は、信頼構築や傾聴、見落とされがちな点に気づく力として活きています。一方で米国のビジネスは、スピードや率直なコミュニケーション、大胆な意思決定を重んじます。
私はどちらか一方を選ぶのではなく、橋渡しをしてきました。日本的な緻密さで土台を整え、アメリカ的な決断力で前に進む。その組み合わせが、熟慮と実行のバランスを生みます。
コミュニティづくりでも、この文化の架け橋はより重要です。多様なバックグラウンドを持つ家族が「自分ごと」として受け入れられる設計を目指す——両方の文化を生きる自分だからこそ、多様性が “喜ばれる” 場をデザインできるのだと思います。

Q: 近年、近隣の安定に寄与する「ライフスタイル・モデル」が注目されています。従来型開発と比べて、なぜそこまで強いのでしょう?
A: ライフスタイルモデルの核心は「安定」を生むことです。従来は販売を急ぐ前提で設計されることが多く、住み替えが頻繁になり、近隣が流動的になりがちでした。
ライフスタイル・モデルは最初から長期賃貸を念頭に置いて計画します。所有のプレッシャーなく、新築品質・デザイン・アメニティを享受できる。時間の経過とともに人が定着し、子どもが一緒に育ち、友人関係が続き、「帰属感」が育つのです。
ビジネス面でも安定は全方良しです。居住者は一貫性とコミュニティを得て、投資家は堅調な稼働と安定収益を得る。都市にとっては、分断ではなくレジリエンスの高い街区が生まれる。
私にとって、これは単なる金融モデルではありません。人が健やかに暮らせる環境を“先に” つくる方法であり、人が繁栄すれば投資も自然と実りを分かち合えるのです。
Q: 収益性と、「人が本当に“家”だと感じられる場」をつくる使命はどう両立していますか?
A: 両立というより、むしろ相互強化だと考えています。投資家に確かなリターンを届ける規律は、プロジェクトの持続性を担保します。しかし、収益だけでは私自身は動かされません。人が安心し、つながり、くつろげる場所をつくることが原動力です。
そして真実はシンプルで、人中心に設計すると収益は後からついてくる。コミュニティへの所属意識の強くなった家族は長く住み、住まいを大切にし、近隣の安定に寄与します。その安定が、財務の強さへと反映される。
だから私は「バランス」ではなく「アラインメント(整合)」だと捉えています。財務の健全性と人間中心設計の両方を尊重すると、紙の上だけでなく “現実の生活” でも意味ある成功になります。
Q: Home at Maricopa で、原点を思い出させてくれたエピソードはありますか?
A: あります。第1期の入居直後、ある若いご家族が「ここに来てから子どもが本当に楽しそう。毎日外に走り出して遊ぶんです。やっと “家” だと感じられます」と話してくれました。
その言葉は本当に胸に響きました。私たちがつくっているのは単なる家ではなく、人の暮らしの背景そのもの。プールやクラブハウス、小さな緑地は、子どもの笑い声や友情や安心感が生まれる “舞台” なのだと。
もちろん数字も大切です。でも、日々の質感を変えられるかもしれないという実感こそが、私を動かし続けます。人が「ただいま」と言える場所を増やす——それが私にとっての本当の報酬です。
Q: 日常の視点で設計するとおっしゃいます。住む人の体験に効く、意図的な “ささやかな工夫” には何がありますか?
A: 例えば大きなドッグラン。一見ペット向けアメニティですが、実際には同じ関心を持つ隣人が自然に集まり、会話が生まれ、つながりが育つ場所になっています。散歩が人と人をつなぐ橋になるのです。
もう一つは、ジムを子ども用遊び場の真横に配置し、大きな窓で見渡せるようにしたこと。お母さんがトレッドミルで走りながら、外で遊ぶ子どもを見守れる。小さな工夫ですが、「不安な運動」を「安心のセルフケア」に変えます。
クラブハウスやプールも、日陰の席、開放的な動線、ふと立ち寄りたくなる居場所づくりを徹底。派手さではなく、「ここにいたい」と思える余白を設計しています。
Q: コミュニティ開発には常に課題が伴います。レジリエンスやリーダーシップを最も教えてくれた障害は?
A: 技術的な課題以上に、「人」の課題から多くを学びました。初期には遅延があり、関係者の不満も生まれました。そこで私は “強く押す” のではなく、まず “聴く” ことを選びました。建築家、施工者、入居待ちの家族——多様な声に耳を傾けることで、解が“ともに” 立ち上がってくる場が生まれます。
また、意思決定の文化差も壁でした。慎重さに傾く私と、スピードを重んじる米国流。その緊張を「対立」ではなく「均衡」と捉え直し、忍耐×決断を強みに変えました。
レジリエンスは単なる “我慢強さ” ではなく “適応力”。リーダーシップは “管理” ではなく “信頼”。同じ障害でも、こちらの関わり方次第で、チームを分断も結束もさせ得る——それを学びました。
Q: これから先、あなたの開発が次世代へ残すレガシーは、どのようなものだと考えていますか?
A: Home at Maricopa では、アパートを建てただけではなく “コミュニティの火を灯した” ことを誇りに思います。最初の家族が引っ越してきた日に、すでに生活は始まっていました。公園で遊ぶ子ども、ドッグランで出会う隣人、ジムで子どもを見守りながら運動する母親——そんな日常の断片が、帰属感の土台になります。
さらに嬉しいのは、その生命感が次の投資を呼び込むことです。大型店舗やサービスが生まれ、エリアに人を引き寄せ、多様性と地域経済が育つ。成長と包摂の循環を目の当たりにできたのは、私のキャリアで最もやりがいのある経験の一つです。
私が残したいレガシーは、家は単に雨風をしのぐ器ではなく、人の可能性に弾みをつける場所。そこに暮らすことで、つながりが生まれ、機会が広がり、多様性が花開く。壁や屋根を超えた “豊かにつながる人生” という可能性を、次世代に手渡していきたいのです。